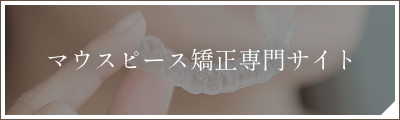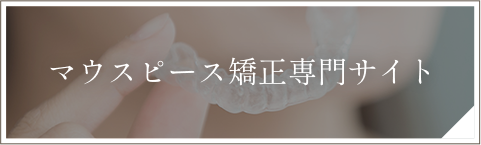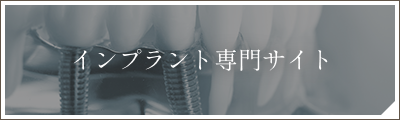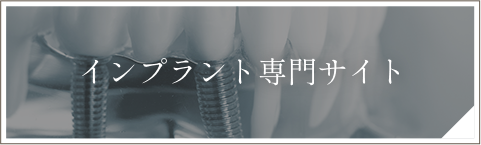「今まで“自己流”で歯を磨いていたけど、正しい歯みがきのやり方が知りたい」
「歯みがきって、どれくらい時間をかければいいのかな?長い方がいい?」
毎日の歯みがき。
皆様は、どのようなやり方で歯を磨いていますか?
“自己流”で、ゴシゴシと強い力で歯を磨いていませんか?
ゴシゴシと強い力での歯みがきなど、自己流の磨き方はあまり適切ではない場合も。
今回は、「正しい歯みがきのやり方」および「よくある間違った歯みがき」について、お話しします。
目次
■正しい歯みがきのやり方
◎軽い力で、同じ面の歯をぐるりと磨きましょう
正しい歯みがきのやり方についてですが、一人ひとりのお口の中や歯並びは異なるため、「これで完璧です!」のような方法は実はありません。
全員に対して100%問題ない、といったやり方はありませんが、歯みがきの基本は以下の2つになります。
[正しい歯みがきの基本]
-
軽い力で磨く
ペンを持つように、親指・人差し指で軽く歯ブラシを持つのがオススメです。ペンを持つように歯ブラシを持つことで、力の入れすぎによる歯・歯周組織へのダメージを防ぎやすくなります。
-
同じ面の歯をぐるりと磨く
歯の表側なら表側をぐるり、
歯の裏側なら裏側をぐるり、
歯の噛み合わせ面なら噛み合わせ面をぐるり、
というように、同じ面の歯をぐるりと磨きましょう。
同じ面の歯をぐるりと磨くといったルールを作ることで、磨き忘れを防ぎやすくなります。
—–
上記の2つを基本として、以下のような点に留意することで、歯についた歯垢・食べかすなどの汚れを効率的に落としやすくなります。
①歯1~2本につき、歯ブラシを小刻みに10~20往復させて磨く
歯ブラシを小刻みに往復させることで、歯と歯の隣接面(歯と歯のすき間)に近い部分や歯周ポケット付近の汚れをかき出しやすくなります。
②前歯の裏側は歯ブラシを立て、歯ブラシの“かかと”で磨く
歯ブラシの“かかと”とは、歯ブラシの毛束のお尻部分です。
歯ブラシを立て、歯ブラシのかかとで磨くことで、前歯の裏側の汚れをかき出しやすくなります。
③歯の噛み合わせ面は歯ブラシを斜めに傾け、歯ブラシの“つま先”で磨く
歯ブラシの“つま先”とは、歯ブラシのヘッドに近い部分の毛束を指します。
歯ブラシを斜めに傾け、歯ブラシのつま先で磨くことで、歯の噛み合わせ面の溝の汚れをかき出しやすくなります。
④奥歯の内側(舌側)は歯ブラシを斜めに立て、挿し入れて磨く
歯ブラシを斜めに立て、歯ブラシを斜めに挿し入れて磨くことで、奥歯の内側の隣接面(歯と歯のすき間)に近い部分の汚れをかき出しやすくなります。
⑤奥歯の外側(頬側)をしっかり磨く
奥歯の外側(頬側)は歯ブラシのヘッドが入りにくく、磨き残しが出やすいです。
歯ブラシのヘッドを入れるときに多少、窮屈さを感じるかもしれませんが、奥歯の外側(頬側)も忘れずにしっかり磨きましょう。
⑥歯と歯ぐきの境目は、歯ブラシのヘッドを斜め45度にして毛先を当てる+歯周ポケットの中に毛先をすべり込ませるようにして磨く
歯と歯ぐきの境目の歯周ポケットは、歯垢・食べかすなどの汚れが溜まりやすいです。
歯ブラシのヘッドを斜め45度にして、歯周ポケット付近に毛先を当てることで、歯周ポケットの中に毛先をすべり込ませやすくなります。毛先をすべり込ませる動作により、歯周ポケットの中の歯の根面についた汚れをかき出しやすくなるメリットも。
■ありがちな“自己流”の間違った歯みがきの例
◎“自己流”の適切ではない歯みがきは、あまり良くありません
以下のような歯みがきは歯・歯周組織を傷つけてしまったり、磨き残しの原因になりやすいです。
[間違った歯みがきの例]
-
ゴシゴシと強い力で歯を磨く
-
同じ面の歯をぐるりと磨かず、あっちこっちの面に飛んで歯を磨いている
-
歯ではなく、歯ぐきを磨いている
-
適切な角度で歯ブラシの毛を歯に当てていない
■歯みがきにかける時間、歯ブラシの毛の硬さ、歯ブラシを交換するペース、歯磨き粉の量、歯みがきの回数・タイミングなど
◎毎食後3分以上、就寝前は10分程度の歯みがきが理想的です
歯みがきにかける時間についてですが、
-
毎食後:3分以上
-
就寝前:10分程度
を目安にブラッシングするのが理想です。
{時間を気にするのではなく、「歯についた歯垢・食べかすを落とす」&「軽い力で歯を磨く」ことが重要です}
目安の分数をお伝えしましたが、実は、歯みがきにかける時間はそれほど重要ではありません。
時間をかける・かけないではなく、歯みがきでは、適切にブラッシングを行い、「歯についた歯垢・食べかすを落とす」ことが重要になります。
{歯みがきに時間をかけすぎ(磨きすぎ)の方は要注意}
丁寧に磨こうとするあまり、強い力で時間をかけて歯を磨くと、歯の表面を覆うエナメル質が削られてしまうおそれがあります。
強い力での歯みがきにより、歯ぐきが下がってしまうことも少なくありません。強い力での磨きすぎが原因で、知覚過敏がひき起こされるケースも。
◎歯ブラシの毛の硬さは「ふつう」「やわらかめ」の物を
「かたい」歯ブラシは、歯・歯周組織を傷つける原因になる場合があります。歯ブラシの硬さは「ふつう」や「やわらかめ」を選ぶようにしましょう。
◎1ヶ月に1回は歯ブラシを交換しましょう
歯ブラシの毛先が開いている・開いていないに関わらず、1ヶ月に1回は歯ブラシを交換しましょう。
毛先が開いている歯ブラシを何ヶ月も使っていると、清掃性が低下してしまうことがあります。
◎歯磨き粉を用いる場合は、年齢に応じて、適切な量の歯磨き粉を
日本口腔衛生学会をはじめとする各歯科学会では、フッ素が含まれた歯磨き粉の使用量を以下のように推奨しています(※)。
(※)日本口腔衛生学会・日本小児歯科学会・日本歯科保存学会・日本老年歯科医学会「4学会合同のフッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法」(2023)より引用。
|
年齢 |
歯磨き粉の量 |
フッ素濃度 |
歯みがきの回数 |
|
生後6ヶ月頃~2歳 |
米粒程度 (1~2mm程度) |
900~1,000ppm |
就寝前の1回を含め、1日2回 |
|
3~5歳 |
グリーンピース程度(5mm程度) |
900~1,000ppm |
就寝前の1回を含め、1日2回 |
|
6歳以上の子ども~大人 |
歯ブラシの毛束全体 (1.5~2cm程度) |
1,400~1,500ppm |
就寝前の1回を含め、1日2回 |
{歯磨き粉の使用は必須ではありません}
むし歯の予防効果を高めるには、歯質を強化する作用を持つフッ素配合の歯磨き粉を使うのがオススメです。ただし、フッ素配合の歯磨き粉を含め、歯みがきでは、歯磨き粉の使用は必須ではありません。
(今回ご紹介したような)適切な方法で歯を磨けているのであれば、歯磨き粉を使わなくても、歯垢・食べかすなどの汚れを落とすことは可能です。
◎歯みがきの回数・タイミング
{毎食後&就寝前の歯みがきが望ましいです}
上記の表では1日2回の歯みがきとなっていますが、毎食後の歯みがきが望ましいです。
朝食・昼食・夕食を食べる方は、1日3回、毎食後に歯を磨きましょう。間食を取ったときも、歯を磨くことが大切です。
…とは言うものの、毎日のお仕事・学業・家事などで忙しく、めんどくさい、歯を磨く気力が出ないときもあるかもしれません。
めんどくさい、歯を磨く気力が出ないときは、食後、お口ゆすぎだけでも行いましょう。お口ゆすぎを行い、少し気力が出たときに歯を磨いてください。
{1日の中で、重要な歯みがきのタイミングは「就寝前」}
毎食後の歯みがきがめんどくさい、時間がない場合は、就寝前の歯みがきだけは行いましょう。就寝前の歯みがきが大事な理由は、就寝中はむし歯・歯周病菌を含む細菌が口腔内で繁殖しやすいためです。
{酸度が高い飲食物を飲食した後の歯みがきについて}
炭酸飲料やお酢、かんきつ類の果物など、酸度が高い飲食物の飲食後は、酸の作用で歯が溶け、エナメル質がやわらかくなっています。
エナメル質を傷つけないようにするために、酸度が高い飲食物の飲食後は、30分経ってから歯を磨きましょう。
【適切なやり方で歯を磨き、むし歯・歯周病の進行を抑えましょう】
{歯科衛生士による歯みがき指導を行っています}
当院では、歯科衛生士による歯みがき指導(歯みがきのやり方のアドバイス)を行っています。
歯みがき指導をご希望の方は、受付・歯科医師までご遠慮なくお申し出ください。お電話・WEBからのご予約の際に、「歯みがき指導を受けたい」旨をお伝えいただいてもかまいません。
—–
むし歯・歯周病の進行を抑えるには、適切なやり方での歯みがき+歯間清掃が重要です。
適切なやり方での歯みがき+歯間清掃に加え、歯科医院で受ける定期検診も大切。
歯科医院にて定期検診を受けることで、ご自身のセルフケアでは落とせない歯の汚れを落としやすくなります。定期的な検診により、むし歯・歯周病などのお口の病気や異常の早期発見・早期治療にもつながります。
日頃から、適切なやり方での歯みがき+歯間清掃を行い、併せて、歯科医院で定期検診を受け、むし歯・歯周病の進行を抑えましょう。